お別れの後の不調や鬱っぽさ。それはグリーフかもしれません。
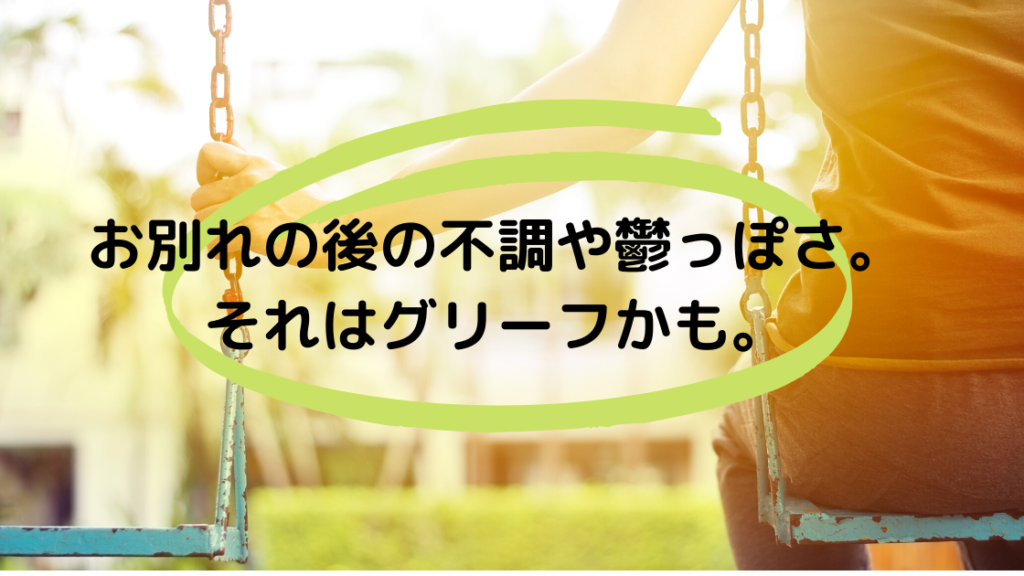

死別や離別を経験した後に、体調を崩したり、鬱っぽい状態が続いているという場合、グリーフ反応が起きているかもしれません。
グリーフ(grief)という言葉をご存知でしょうか?
日本語に訳すと「悲嘆」という意味で、大切な人を失った時に心身に起きる影響や変化のことをいいます。
今日はグリーフが心身にもたらす影響についてお話ししていきます。
グリーフという言葉を聞いたことがありますか?
グリーフの意味からお話ししていきましょう。
今までの人生で、あなたはどんなものを失ってきましたか?
大切な人を亡くした経験がありますか?
その時、どんな状態になりましたか?
’’悲しくて涙が止まらなかった”
”しばらく思い出しては切なくなって苦しい気持ちが続いた’’
何かしら、平常時の自分ではいられなかったのではないですか。
大切な存在との別れの後に陥った「平常時の自分ではいられない状態」こそが、グリーフの反応だと言っていいと思います。
愛する人との死別によって引き起こされる悲しみなどの悲嘆感情、それにまつわる反応のことを「グリーフ」と言います。
広義には、死別以外であっても、離婚や役割・住宅・身体の健康等、何か自分にとってかけがえのなかったものを失うことで生じる強い悲しみも、グリーフとして捉えられます。
大切な存在を失った時のショック状態からなかなか抜け出せなかったり、悲しみなどの強い感情や落ち込みが続いていたり、その苦しみは千差万別です。
「自分はおかしくなってしまったのではないか?」と自分のことが心配になってしまうほどに、自分が自分でなくなったみたいな不安定さを感じる場合もあります。
グリーフは、弱い人に起きるということではなく、ましてや病気になったということでもなく、誰にでも起こりうる自然な反応です。
でもだからといって、やり過ごせばいいや、時間が解決してくれると、軽視するのは禁物です。
苦しい感情や思いに蓋をしてずっと我慢を重ねていると、そのストレスから生きづらさや重大な病気に繋がってしまう恐れもあります。

人生は喪失だらけ。誰だってグリーフを経験する可能性があります。
大切な人との別れ、離婚や失恋、失業、転職、子離れ、身体の一部を失くすなど、人生は喪失だらけです。
考えてみれば、生まれた時にも喪失を経験しています。
お母さんの子宮のお部屋を出て、へその緒も切られて、とお母さんと一体化していた環境から卒業するわけですから。
もちろん、すべての喪失体験がグリーフに繋がるわけではありません。
でも、大好きな人との死別経験など自分にとって大きな別れがあった場合には、生じるダメージやストレスも大きくなるでしょう。
人生なにかを失いながら生きていかなくてはいけないのなら、喪失と上手に付き合うための知識やスキルを持っていた方がいいですね。

グリーフ状態の時に起きやすい反応
では次に、グリーフに陥った時、具体的にどんな反応が出やすいのかということについてお話ししていきますね。
喪失体験の後、体調を崩したり、身体面に不調を感じる人は多いです。
一番気が付きやすい反応であるともいえるでしょう。
たとえば、このような反応が現れます。
-
疲労感、体力の低下によって活動量が減る。
-
睡眠障害(眠れない、もしくは寝ても寝ても眠い)
-
食欲への影響(食欲がない、味がしない、食べすぎる)
-
免疫力の低下(感染症、扁桃炎、口内炎や帯状疱疹、突発性難聴などに繋がりやすい)
-
動悸、息切れなどを感じやすい。呼吸が浅くなり息苦しさがある。
-
体の痛み(胃や胸部、肩こりなど)。故人が訴えていた場所と同じところに痛みを感じる。
グリーフで生じる症状なのか病気なのか、判断がつきにくい場合は、きちんと診察をうけてくださいね。
それ以外にも、こんな症状が起きやすくなっています。
グリーフが身体面や感情面に影響が出ることはイメージしやすいと思いますが、そのほかにも広範囲にわたって反応が出ることがあります。
たとえば、認知機能、集中力、人間関係といった面にも影響が出やすくなります。
-
悲しみ、不安、怒りなどがふいに湧いてきて、自分で感情のコントロールができない。
-
人の話を集中して聞けなかったり、ひとつのことを集中して取り組めない。
-
人と会うのが億劫になって孤立しやすい。孤独感を感じる。
-
時間の感覚がなくなり、生活のリズムがつかめなくなる。
-
今まで難なく出来ていたことなのにとても難しく感じる。
-
物忘れが激しくなったり、遅刻をしやすくなる。
-
自分が変わってしまったように感じてすべてに自信がなくなる。
-
ずっと過去に思いを馳せ、後悔や未練を感じることが多くなる。
- 難しい本が読めない、活字が目に入ってこない。
- 生きる意味が見いだせない、活力の欠如。
グリーフがここまで影響をもたらしていることは、あまり知られていないかもしれませんね。
たとえば、グリーフによって認知機能が低下するということを知っていましたか?
物忘れがひどくなった高齢のご家族に対して「ボケちゃった?」と心配している方もいますが、喪失体験の後にそのような変化があったとしたら、もしかしたらそれは認知症ではなくて、グリーフなのかもしれません。
このように「グリーフなのかも?」と気付ける視点を持っていることで救いになることがあります。
まずは、グリーフによっていろいろな面に影響が出るんだ、ということを覚えておいてくださいね。
グリーフの視点を持つことで、自己理解が進んだり、適切なケアに繋げていくことができます。

グリーフの状態から楽になっていくために。
死別や離別の後に、このような症状に悩まされていたらどうしたらいいのでしょうか。
ここまで読んでいただいて「私って、もしかしてグリーフかな?」と思ったら、喪失体験をした後の自分について思い返してみることをお勧めします。
- 本当は悲しかったのに、十分にその悲しみを味わうことがないまま、心に蓋をしていませんか?
- 弱音を吐いてはいけないと、我慢していませんか?
- 前を向いて頑張らなくちゃと自分で自分を鼓舞し続けていませんか?
日本では「人前で取り乱すことは良くない」と思う人が多く、感情的にならないようにセーブする傾向があります。
心の中にさまざまな気持ちが湧きあがっていても、周りの目を気にしたり、自分を元気づけようとしている人に嫌な思いをさせたくないと思えば、自分の気持ちを抑えて我慢してしまうようになります。
その我慢している思いや感情を、安心できる場で自分らしく表現することができると、少しづつ心が元気になっていきます。
例えば、何か嫌なことがあった時に、信頼できる誰かに話を聞いてもらうことで、心が軽くなったり、気分がすっきりしたことはありませんか?
喪失を体験した時も同じように、心の中にため込んでいたものを表に出すことができるようになると、気持ちも徐々に整理され、楽になっていくことが多いのです。
安心して自分の思いや感情を出せる場所を見つけていくことから始めましょう。
ひとりで向き合うことは難しいと感じる方は専門家のグリーフケアにぜひ支援を求めてください。
でも、本当は亡くなった人と対話ができたらいいのに、と思いませんか?
愛する存在を亡くして悲嘆に苦しんでいる人が抱く究極の願いは「あの人をもう一度この世に取り戻したい」とか「あの人と過ごしていたあの頃に帰りたい」ということかもしれません。
叶わない願いだと分かっていながらそのような想いが止まらない、というご相談も受けます。
グリーフの苦しみは、大切な人とのコミュニケーションが未完で終わっていることに起因していることがあります。
愛する人が亡くなる前に、聞いておきたかったこと、伝えておきたかったこと、してあげたかったこと、分かってほしかったこと、そのような後悔や自責の念があることがグリーフを深めていきます。
そして相手が亡くなっていることで、そのコミュニケーションは未完了にならざるを得ません。
凍結してしまったコミュニケーションが再開できたら、どうでしょうか?
まとめ
- グリーフ(grief)とは、直訳すると「悲嘆」という意味で、大切な人を失った時に心身に起きる影響や変化のことをいいます。
- グリーフの反応には、感情面だけでなく、体調面、身体的な変化、人間関係、認知機能など、日常生活のいろいろな部分に影響が出てくることがあります。
- グリーフは病気ではなく、誰にでも起こりうる自然な反応です。
- 喪失体験の後に、不調や不安定さがあっても、それがグリーフの反応だと気付く人は少ないかもしれません。
- グリーフの知識を身に着けると、心身の状態を理解しやすくなります。
- 大切な存在を失った時には、さまざまな面に影響が出てくるということを覚えておけば、「自分は変になったわけじゃない」と少しほっとできるかもしれません。
- グリーフの状態から楽になっていくために、抑え込んできた感情や思いを安心出来る形で吐き出してみましょう。
- 自分の中にあるものを表現していくことは、グリーフワークになります。
- グリーフの時にはひとりで頑張りすぎず、サポートを積極的に受けてください。
- グリーフケアの専門カウンセリングやセラピーもありますので、必要に応じて専門的な支援を取り入れていくことも良いと思います。
- 大切な存在を失った悲しみと上手に付き合っていけることを願っています。

